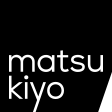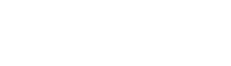防災について考える
2024/9/10

毎年9月1日は防災の日。その日を含む1週間は「防災週間」とされ、防災訓練が行われたり、防災知識普及のためにさまざまなイベントが開催されます。
近年は地震のほか、地球温暖化の影響で台風が大型化したり、線状降水帯の発生で豪雨が降り続く水害も増えています。
そこで今回はいざというときに備えて、防災対策について考えていきたいと思います。
■目次
日頃からできる防災対策

災害はいつ発生するかわかりません。
そのため、普段から家庭や職場で災害が発生することを想定した準備を整えておくことが大切です。
防災グッズや非常食を準備しているかたも少なくないと思いますが、防災用品は準備だけでなく定期的に管理や確認を行うことで災害時にすぐ持ち出したり、使用できるようにしておきましょう。
★フェーズフリー防災
近年では日常と災害時を区別しない「備えない防災」と呼ばれる「フェーズフリー防災」への注目が高まっています。
普段使っている商品やサービスを災害時に役立てるという考え方です。
防災用品は物置などにしまい、非常時に取り出して使うという認識のかたが多いかもしれませんが、そうすると何がどのくらい備蓄されているか、食料の消費期限は切れていないかなどを定期的に確認する必要があります。
さらに、いざというときに役に立たないという恐れも…。
フェーズフリー防災は災害が起きたときのために準備するのではなく、日常的に使っているものを災害時にも役立てるという防災の新常識です。
★ローリングストック
フェーズフリー防災の代表的なものが「ローリングストック」です。
防災用のロングライフ商品を買うのではなく、いつも使っている加工食品や保存食を少し多めに買っておく「日常備蓄」です。
日常的に消費し、また購入するという流れを習慣化することで、保存食の鮮度も保つことができます。
近年の災害ではさまざまな要因から「在宅避難」を余儀なくされるケースも増えているため、そんなときも普段から食べ慣れた食品であれば非常時も安心して口にできます。
家族それぞれが好きなお菓子や飲み物などをストックしておくのも良いですよ。
★在宅避難用の防災備蓄リスト
在宅避難の場合、ペットボトル入りの飲み物や乾麺、レトルト食品、缶詰、乾物などの保存のきく食料を多めに持っておく必要があります。
食器にラップをかぶせて使うと、食器を洗わなくても済むため、多めに買い置きをしておくのがおすすめです。
カセットコンロは温かい食事を調理することができますし、災害時だけでなく鍋やキャンプなどでも役立ちます。
また、水で口をすすぐ必要がない液体ハミガキなども準備しておけば、断水時にも歯をみがけます。
【食料・飲料】
・飲料水(1日3L×10日分)
・食料(日常の食材を10日分)
【貴重品】
・現金
【情報収集用品】
・モバイルバッテリー
・ラジオ
【身につけるもの】
・ヘルメット
・感染予防マスク
・ポリ手袋
・レインウェア
【衛生用品・薬】
・痛み止め
・消毒液
・滅菌ガーゼ
・三角巾
・止血シート
・包帯
・目薬
・ウエットタオル
・消臭・抗菌剤
・ハブラシ
・液体ハミガキ
・災害用トイレ
・トイレットペーパー
【その他】
・ポリ袋
・ランタン
・ライター
・筆記用具(油性ペン)
・ラップフィルム
・ブルーシート
・卓上カセットコンロ
・カセットガス
・ポータブル電源
★外出時携帯用の防災備蓄リスト
外出時に災害に遭うことも考えられます。そんなときに備えとして持ち歩いてほしいものがこちらのリストです。
懐中電灯やラジオ、トランシーバーはスマートフォンの機能で代用できますから、スマホ用のモバイルバッテリーを持ち歩くのがおすすめです。
モバイルバッテリーは普段のバッテリー切れにも使えるので便利ですよね。
歯みがきのトラベルセットも日常の口臭予防と災害時のお口の健康維持に使えるため、普段から持ち歩きたいものです。
【食料・飲料】
・ゼリー飲料
・おやつ
【貴重品】
・現金
【情報収集用品】
・モバイルバッテリー
・ラジオアプリ
【身につけるもの】
・感染予防マスク
・ポリ手袋
・レインウェア
・大判のハンカチ
【衛生用品・薬】
・痛み止め
・止血シート
・目薬
・ウエットティッシュ
・流せるティッシュ
・消臭・抗菌剤
・災害用トイレ
・ハミガキトラベルセット
【その他】
・ポリ袋
・笛
・ペンライト
・カイロ(冬)
・筆記用具
★救急箱の確認

救急箱の中身に決まりはありませんが、普段使うものを清潔な入れ物に入れておくようにしましょう。
滅菌ガーゼや薬には使用期限があり、テープ類は古くなると粘着力が弱くなります。
そのため、防災備蓄のチェックとあわせて救急箱のチェックもしておくと良いでしょう。
災害時のオーラルケア

災害時は断水などが起こると水が不足するため、飲料水が優先され、貴重な水を歯みがきに使うことがためらわれます。
そうすると口の中を清潔に保つことが難しくなり、細菌が増殖することで健康にもさまざまな影響を及ぼすこともあります。
特に高齢のかたは誤嚥性肺炎が起こりやすくなるので注意が必要です。
★災害時のオーラルケア方法
【液体ハミガキがある場合】
水やお茶のかわりに液体ハミガキを使う。水でのすすぎは不要。
【水が少ない場合】
① 水約30mLをコップに準備し、コップの水でハブラシを濡らしてから歯みがきを開始。
② ハブラシの汚れをティッシュペーパーで拭き取り、また歯みがき。これを繰り返す。
③ 最後にコップの水で2〜3回すすぐ。一気に含むのではなく、数回に分けるほうがきれいになります。
【すすぎに使える水もハブラシもない場合】
・ハンカチやティッシュ、タオルなどを指に巻き付けて歯を拭い、汚れを取る。
・お口をキレイに保つはたらきのある唾液を出すようにする。
ドラッグストアで備える防災グッズ

日常的に使う常備薬や衛生用品、季節的なものは、食料品と同じようにローリングストックがベスト。
ドラッグストアなら防災グッズとしても使えるアイテム幅広く、気軽に購入できるのも魅力です。
救急箱のストックや防災グッズとしてもおすすめのmatsukiyo商品をピックアップしたので、チェックしてみてくださいね。

常備薬としても、防災用としても必須の鎮痛剤。

ちょっとした切り傷にもサッと貼れる!ミシン目入りでハサミ不要も◎。

ノンアルコールタイプはお子様や肌の敏感なかたでも使えて便利!
ウエットティッシュはアルコールタイプとあわせて常備しておきたい。

非常時はお風呂に入れないときに、日常的には気になる汗やニオイ対策に使えます。

水道が使えないときは食器をくるんで洗い物を減らしたり。ちょっとした止血にも。

常用しているサプリメントなどは、備蓄しておくと◎。日常生活をつなげる安心感にもつながります。
個人でできる減災の取り組み

減災とは災害によって被る被害を最小限に抑えるため、あらかじめ行う取り組みのことを指します。
自然災害の発生を防ぐことは難しいため、災害が起こることを前提に、被害をいかに軽減させるかを目的とします。
そんな減災の取り組みで個人ができる7つの備えをご紹介します。
1.自助・共助の意識を持つ
自助は自身の身を守ること、共助は地域や身近にいる人同士で助け合うことを意味します。
行政からの支援が行き届くまで時間がかかってしまう可能性もありますから、「自分の身を守るためにできること」「家族でできること」「近隣住民とできること」を考えておくことが自助・共助による減災につながります。
2.災害時の地域の危険を把握する
ハザードマップで自分が住んでいるエリアや通勤通学などで行き来するエリアが災害時にはどのような被害にあう可能性があるか事前に確認しておきましょう。
ハザードマップには自然災害が発生したときの様子や避難、救護活動に必要な情報も掲載されています。
避難経路や避難場所を把握し、いざというときに焦ることなく行動できるようにしましょう。
3.地震に強い家をつくる
自宅の耐震性に不安があれば耐震診断を受けましょう。
耐震診断を受ける目安として2000年以前に建てられているかどうかがひとつのポイントになります。
2000年以降の建物は新耐震基準で建てられていますが、適切でないケースもあるため、現在の耐震基準を満たしているかどうか耐震診断を受けることをおすすめします。
4.家具を固定する
背の高い家具や重い家電などは倒れた時に二次被害を生む可能性があります。そのため、家具は壁や床に固定しておきましょう。
窓ガラスなどが飛び散らないように、飛散防止フィルムを張っておくこともおすすめです。
家具を固定することは自分だけでなく、家族の身を守ることにつながるということを覚えておきましょう。
5.日ごろから非常用持ち出し袋の準備や備蓄をする
外出時は「身分を証明するもの」(免許証、保険証、診察券、病院や処方箋のメモ)「状況を把握できるもの」(ラジオ、メモ、筆記用具)「閉じ込められた時のためのもの」(笛、水、食料、ハンカチ)を用意しましょう。
自宅では「避難するためのもの」(懐中電灯、履き慣れた靴、手袋)「生きるためにないと困るもの」(薬、飲料、食料、銀行関連)という観点で準備をしましょう。
6.家族で防災会議を行う
災害時の連絡先や連絡方法、合流場所を家族内で共有しておくことも大事です。
災害発生時に家族が一緒にいるとは限らないので、離ればなれになっても再会できるように話し合いをしておきましょう。
また、子どもが保育園・幼稚園・小中学校に通っている場合は災害時の対応についての取り決めを忘れずに確認しておきましょう。
7.地域とのつながりを大切にする
子どもやお年寄り、障がいのある人は災害時に支援が必要な場合もあるため、普段から近隣の人たちとコミュニケーションをとっておくことも大切です。
自分のまわりに支援が必要な人はいないか、また支援が必要な家族がいる場合は周囲の人にサポートが必要なことを知っておいてもらうようにしましょう。
あいさつなど、普段の声かけがいざというときの助け合いにつながるものです。
応急手当ての知識

災害時は病気や事故が発生しても、救急車がすぐに到着するとは限りません。
そばに居合わせた人が応急手当を行う必要があるということも考えられます。
いざというときのために、消防署の講習会などで応急手当の知識と技術を身につけておくというのも手です。
現在では救命講習会に行く時間がないという人向けに、消防庁ではe-ラーニングで応急手当の基本知識が学べる「一般市民向け 応急手当WEB講習」もありますよ。
応急手当を行うには知識と技術が必要です。
応急手当の講習を受けていれば、より確実に自信を持って行うことができるかもしれません。
自然災害の大型化もあり、災害時の避難のかたちもさまざまです。
9月の防災月間には関連イベントが開催されたり、防災を身近に感じられる機会もあります。防災の日を機に、備蓄品のチェックなど、まずはできるところから防災対策をはじめましょう。
こちらの記事も参考にして、いつ災害が起きても困らない準備を日常生活に取り入れていただけるとうれしいです。
この記事でご紹介しました商品は、全国のマツモトキヨシグループ店舗・ココカラファイングループ店舗(※一部店舗を除く)とオンラインストアで好評発売中です。
記事一覧
-

人はなぜ寒くなると甘いものを欲するの⁉︎
-

11月8日は「いい歯の日」毎日のケアで差がつく“いい歯” を育むヒント
-

秋こそ“ととのう”のベストシーズン!秋のレジャーはサウナで決まり
-

朝食を食べよう!
-

夏の睡眠パフォーマンスを上げる
-

FEM COLUMN④VIOゾーンもボディも白玉美肌ケアを
-

FEM COLUMN③外出時も快適に過ごせる!VIOゾーン用ウェットシート
-

FEM COLUMN②VIOゾーンは専用ソープで優しくケア
-

FEM COLUMN①生理の終わりかけに便利なアイテムがあること知っていますか?
-

顔のシワやたるみは“骨やせ”が原因かも!?
-

食べるファスティングでゆるく身体を整えよう
-

暴飲暴食の時期を乗り切る
-

「セルフラブ」自分を大切にする方法
-

寒暖差による不調に注意!〜冬支度はドラッグストアで〜
-

2024年は“時短”ハロウィンを楽しもう
-

防災について考える
-

紫外線量の多い夏!髪と頭皮のケアも忘れずに
-

フェムケアとフェムテックについて考える
-

梅雨も楽しく過ごそう♪
-

五月の肌トラブルにご注意を
-

朝ごはんや軽食に『マグカップごはん』はいかが?
-

春はなぜ眠くなる???
-

2024年のウェルネス&ビューティトレンド5選
-

年越しそばのあとは年明けうどん!?
-

身体と心も“ととのう” 冬サラダ
-

自分の爪をチェックしてみて! 11月11日はネイルの日
-

2023年のハロウィン! 仮装メイクを楽しもう♪
-

中秋の名月~月美容はじめてみませんか~
-

夏のプールや海! 水遊びシーンのお悩みを解決♪
-

7月7日は七夕とポニーテールの日♡
-

しまい洗いのススメ
-

感染症法のおさらいと今後の感染対
-

マスクを着ける日、着けない日。
-

美容にも健康にも! 大豆パワーで季節の変わり目を乗り切ろう
-

乾燥や花粉で敏感になりやすい春の肌ケア
-

バレンタインデーはチョコレートを楽しもう♪
-

お正月気分をリセットして年明けを気持ちよく過ごそう
-

クリスマスプレゼントはマツキヨココカラで♪
-

11月8日はいい歯の日!お口の健康について考えましょう
-

秋の一大イベント!matsukiyoでハロウィンを楽しもう
-

食欲の秋到来!ついつい食べ過ぎてしまうのは…
-

夏バテを防ぐ食生活って? 汗で失われやすい栄養を取り戻そう!
-

大雨への備えは大丈夫? 防災の日の前に防災用品の見直しも
-

アウトドア遊びの前はマツキヨココカラで準備♪
-

人気のたんぱく質レシピに加えたい食物繊維。常備保存OKな食材でかしこく摂ろう!
-

UVケアの基礎知識を身につけて、日焼け止めを選ぶ
-

マスク生活でも第一印象は好印象を与えたい
-

ペットとの暮らしを快適に! すぐできる抜け毛&におい対策
-

毎日のお風呂タイムを、極上の美容時間に!
-

ノーマスク生活に向けて!見直そう、デンタルケア
-

2021年の記事一覧はこちら!
-

2020年の記事一覧はこちら!
-

2019年の記事一覧はこちら!
-

2018年の記事一覧はこちら!